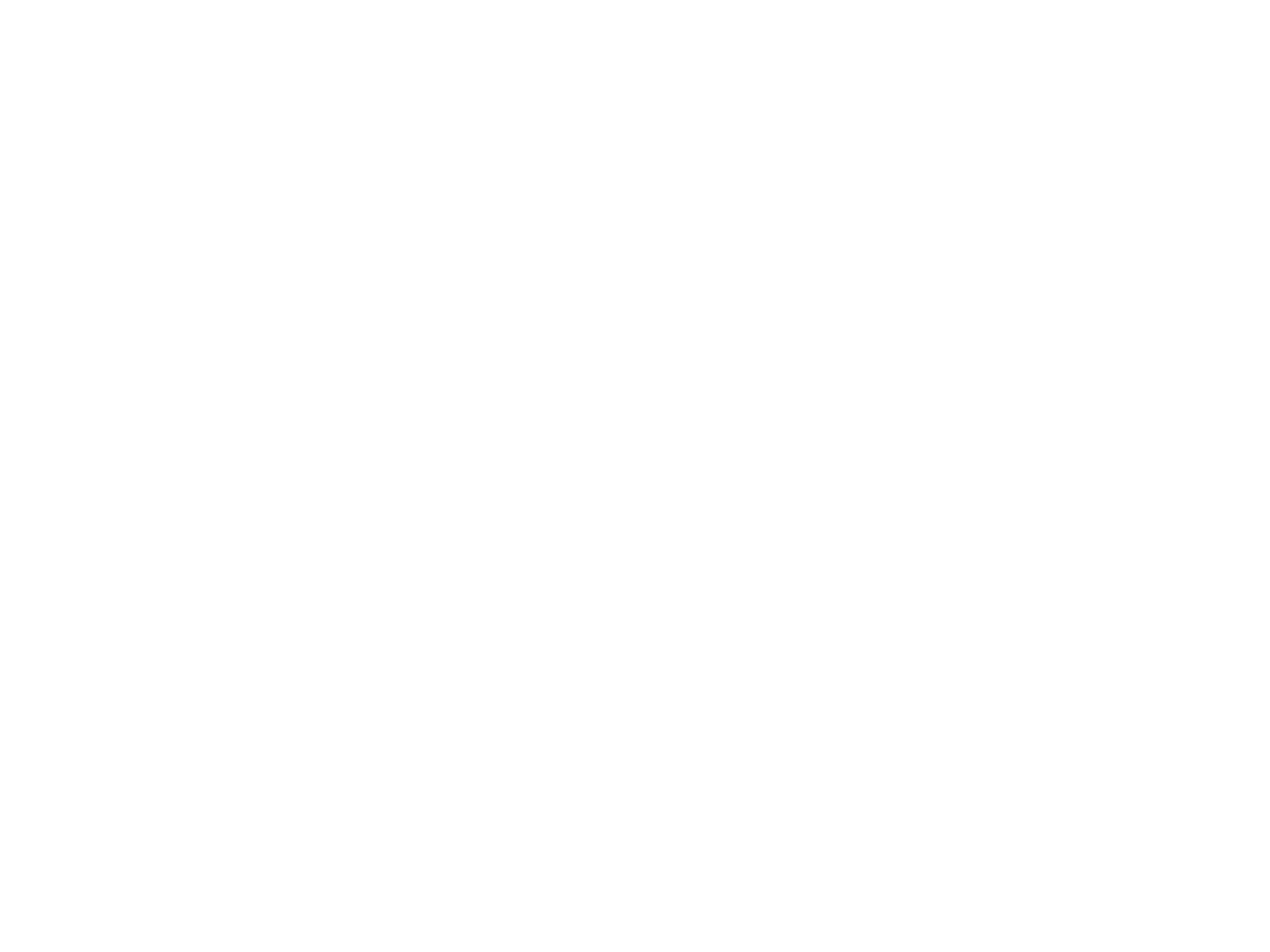京都映画盛り上げ隊!
♯13「京都ヒストリカ国際映画祭」プログラムディレクター 髙橋剣さん

答えてくださった方京都ヒストリカ国際映画祭 プログラムディレクター 髙橋剣さん
京都ヒストリカ国際映画祭が始まったきっかけを教えてください
2000年代半ば、京都府さんと京都の学識者や他メディア企業の方などと行っていた勉強会のなかで「どうすれば海外の映画関係者から注目してもらえるのか」という議論が持ち上がり、映画祭を開催するのはどうか、という話になったんです。そこで歴史ものの映画祭は世界的にも珍しく、また京都の特色も出るのでいいんじゃないかというアイデアを出したのがきっかけです。さらに京都には映画だけじゃなくゲームやアニメもある。ならばクロスメディアで歴史を立体的に描いてみてはどうか、クロスメディア、クロスボーダーをコンセプトにすることで、当時時代劇が下火になり、元気がなかった太秦地域や撮影所の課題を解決する方策になればいいと考えていました。
実際、クロスメディア、クロスボーダーの目線で世の中を見てみると『戦国BASARA』や『パイレーツ・オブ・カリビアン』など、意外と元気な歴史ものがあることに気づかされました。
同映画祭では「時代劇」ではなく「歴史映画」という言葉を使われているようですが、なぜでしょうか?
当時「時代劇」という言葉は“お涙頂戴”や“古めかしい”といったイメージが強く、コンテンツ本来の幅の広さが伝わりにくかったんです。かといって「歴史劇」だと宗教的なイメージが強いように感じていて、ならば新しい概念として「歴史映画」という言い方をしてみようと思いました。私オリジナルの言葉ではないと思いますが、この映画祭と共に定着した感はあります。
「京都フィルムメーカーズラボ」や「太秦上洛まつり」など、さまざまなイベントと連携していますが、各イベントの特徴を教えてください
映画祭とほぼ同時期に始まった「京都フィルムメーカーズラボ」と「京都映画企画市」は、いわゆる作り手、クリエーター向けの企画です。一方の「太秦上洛まつり(当時は太秦戦国まつり)」はコンテンツのショーケース+コスプレ、という位置づけで、一般の人に楽しんでもらう企画として始まり、現在まで続いています。「HISTORICA X」は少し後に生まれた企画ですが、もっとテック系によった企画です。いずれも「歴史もの」という共通点を持って連携しています。

2019年から公式に「京都ヒストリカ国際映画祭」との連動企画となった「HISTORICA X」
上映作品を選ぶうえで大切にしていることはありますか?
3つあります。1つ目は、その国の文化を知らなくても楽しめるか。2つ目は、歴史映画として新しい挑戦をしているか。3つ目は、できるだけ広い観客層を想定しているか。毎年この条件を念頭に置き、作品をチョイスしています。
「京都で映画祭を開催する意義」について、どう考えていますか?
先ほども言ったように、撮影所の「中の人」にも元気になってもらいたいと思って始めた映画祭です。なので撮影所の関係者や、撮影所で映画を撮った監督をゲストに呼ぶことも多く、お客様にとっては「映画との距離が近い」映画祭になっていると思います。
第1回から今まで映画祭に携わられてきて、感じる変化はありますか?
映画祭を始めた頃は「時代劇」というだけで向かい風が吹くような雰囲気でしたが、今はだいぶ世間の理解が進んだように感じます。『るろうに剣心』や『レジェンド&バタフライ』、さらには『SHOGUN 将軍』『侍タイムスリッパー』など、成功事例も出てきていますしね。ヒストリカは観客数で成果を測れる映画祭ではありませんが、新しい歴史映画の予兆、匂いのようなものを嗅ぎ取り、少しずつではありますがお客様の間に広げてこれたのではないかと思っています。
また、京都フィルムメーカーズラボの参加者が映画祭のゲストとして戻ってくるなど、年々映画祭を通して出会った人とのつながりを感じる機会が多くなってきていますね。そうした一朝一夕ではない空気感が映画祭の厚みとしてお客様にも伝わったらいいなと思います。

第16回セレモニーの様子。人気アニメプロデューサーから海外で活躍する監督まで、多彩なゲストが顔を揃えた
2年前から始まった「ヒストリカお座敷」について教えてください
板倉一成(京都ヒストリカ国際映画祭 事務局長)
私は第1回から事務局長として映画祭を受付やロビーから見ていて、お客様が映画と映画の間にある「余白の時間」を楽しめるようなことができないかとずっと考えていました。そんなとき、アメリカで開催される「サウス・バイ・サウスウエスト」という映画、音楽、テクノロジー、アートなど、多様な分野が交差する複合イベントの存在を知り、これと同じように色んなジャンルの人が集まる映画祭にできないかと思ったんです。
ヒストリカで上映する作品にはゲストトークがありますが、当然ながら作品に関係する人しか呼ぶことができません。最初に掲げたクロスメディア、クロスボーダーのコンセプトに立ち返り、映画だけでなくアニメやゲームのクリエイターやそれぞれのジャンルでビジネス面で活躍するゲストが 集まれるような場があってもいいんじゃないか、そんな思いつきから、文化博物館6階にある大きな和室を使って、幅広いジャンルの人たちがフランクかつ親密に交流できる「ヒストリカ お座敷」を開催することにしました。

ヒストリカお座敷:片渕須直「そもそも枕草子には映画を作れる何かがあるのか」
映画祭を初めて訪れる方におすすめの楽しみ方を教えてください
髙橋
今回第3回を迎える「ヒストリカ お座敷」は、上映の合間にぜひ訪れてほしいです。今や、ゲストや来場者が交流する映画祭の重要なハブになっています。あとはやっぱり上映前後のゲストトークですね。上映作品自体はどこで観ても変わらないけれど、ヒストリカでしか聞けないゲストの話は絶対におもしろい。インタビュアーの突っ込みも深くて、単なる“思い出話”で終わらない、クリエイティブに切り込む内容になっています。

『侍タイムスリッパー』上映後のトークの様子
今回、府市協調に関する合意があり、ヒストリカと京都映画賞の連携開催が実現することになりました。今のお気持ちや期待することを教えてください。
京都が「映画のまち」だということは、私たち映画関係者だけでなく、京都に暮らす人々のあいだでもよく語られる話です。 だからこうした流れは喜ばしいことですし、共に寿ぎたいと思います。また、京都映画賞の話をすると、会員になって表彰式に参加するということは、たとえ客席からであってもその映画の価値に貢献することになります。映画は観客あってこそのコンテンツなので、こうした府市協調の取り組みを通し、一般の方々にももっと映画を「自分ごと」として受け取ってもらえるようになればいいなと思います。
今後の展望や、ヒストリカに期待していることがあれば教えてください
来年(2026年)は、映画撮影所が太秦に初めて開設されてから100周年という節目。その歴史を踏まえつつ、映画祭で何らかの特集が組めたらと考えています。また、上映作品の選定方法やテーマ設定は毎年異なりますが、東アジアで制作された作品をもっと発掘したいですね。中国・韓国など、魅力的な歴史映画がたくさんあるはずなので、地道に探していきたいです。
京都映画賞の会員へメッセージをお願いします
今年の京都ヒストリカ国際映画祭は、12月2日から7日まで、京都文化博物館で開催されます。この映画祭にご参加いただき、京都という土地だからこそ生まれる映画の魅力を、ぜひ皆さんと共有できればうれしく思います。
【京都ヒストリカ国際映画祭 概要】
世界でただひとつの“歴史映画”にこだわった映画祭。映画上映に加え、世界各国から映画監督やプロデューサー、スタッフを招いてトークショーを行い、日本映画の発祥の地である京都で、日本映画の魅力を広く海外・国内に情報発信し、映画産業の振興とそれらを支える人材育成・人材交流を図ることによる、さらなる産業振興を目的として開催。
●日程 令和7年12月2日(火曜日)~12月7日(日曜日)
●公式HP 京都ヒストリカ国際映画祭